【第3回】八幡市役所で得た学びと発見!
市役所での初めての会議
8月4日、子ども会議が開かれました。今回はいつもの「ふるさと学習館」ではなく、八幡市役所が会場です。初めての場所に少し緊張しつつも、市役所の方々に直接お話を伺える貴重な機会に、子どもたちの表情はワクワクしているようでした。
キョージュの言葉からスタート
会議の冒頭、キョージュから「インタビューをする上で大切なこと」を教わりました。あいさつをきちんとすること。自分の思いを言葉にして伝えること。相手の話に耳を傾けること。そして、質問やお礼を忘れないこと。どれも当たり前だけれど、だからこそ大事なことばかり。子どもたちは真剣な表情でうなずいていました。

各班のインタビューの様子
小学生A班|竹から広がる新しいアイデア
防災への興味から「竹で防災食を作ろう」と考えていたA班。しかし市役所の方との対話の中で、「竹を通して八幡市の魅力をもっと伝えられるのでは?」という新しい発想が芽生えました。防災だけでなく、地域を楽しく知ってもらう仕掛けづくりへ。子どもたちの目は一気に輝きを増していました。

小学生B班|特産品・公園・ごみ問題に迫る
B班は、特産品や公園、ごみ問題をテーマにインタビュー。特産品は地域の誇りであること、公園は安心できる工夫が必要なこと、ごみ問題はポイ捨てをなくすことが一番大切だということを学びました。「次はポイ捨てを防ぐ看板を見に行きたい」「子どもが安心できる遊び場を調べたい」──取材を終えた後、すでに次のアイデアがどんどんあふれていました。

小学生C班|給食と八幡の魅力をつなぐ
C班は学校給食に注目しました。地元農家やキャラクター「たけんちゃん」とのコラボの可能性を知り、給食の新しい展開を考えています。栄養バランスや費用に気を配りながら作られる給食の裏側にも驚きの連続。中でも「竹炭コロッケ」の復活話には大盛り上がり!給食を通して八幡の魅力をもっと伝える道が見えてきました。これからは農園訪問なども視野に入れ、地域とつながる給食のアイデアを探ります。

中学生班|竹のテントからパーテーションへ
中学生班は「竹で防災用テントを作れないか」と考えていましたが、耐久性の面から実現は難しいと分かりました。市役所の方から「一時避難所で使う簡易パーテーションなら可能性がある」とのヒントをもらい、新たな方向性を見つけました。次回は実際に竹を使って、どのような簡易パーテーションができるかを実験し、現実的な形へとアイデアを深めていきます。
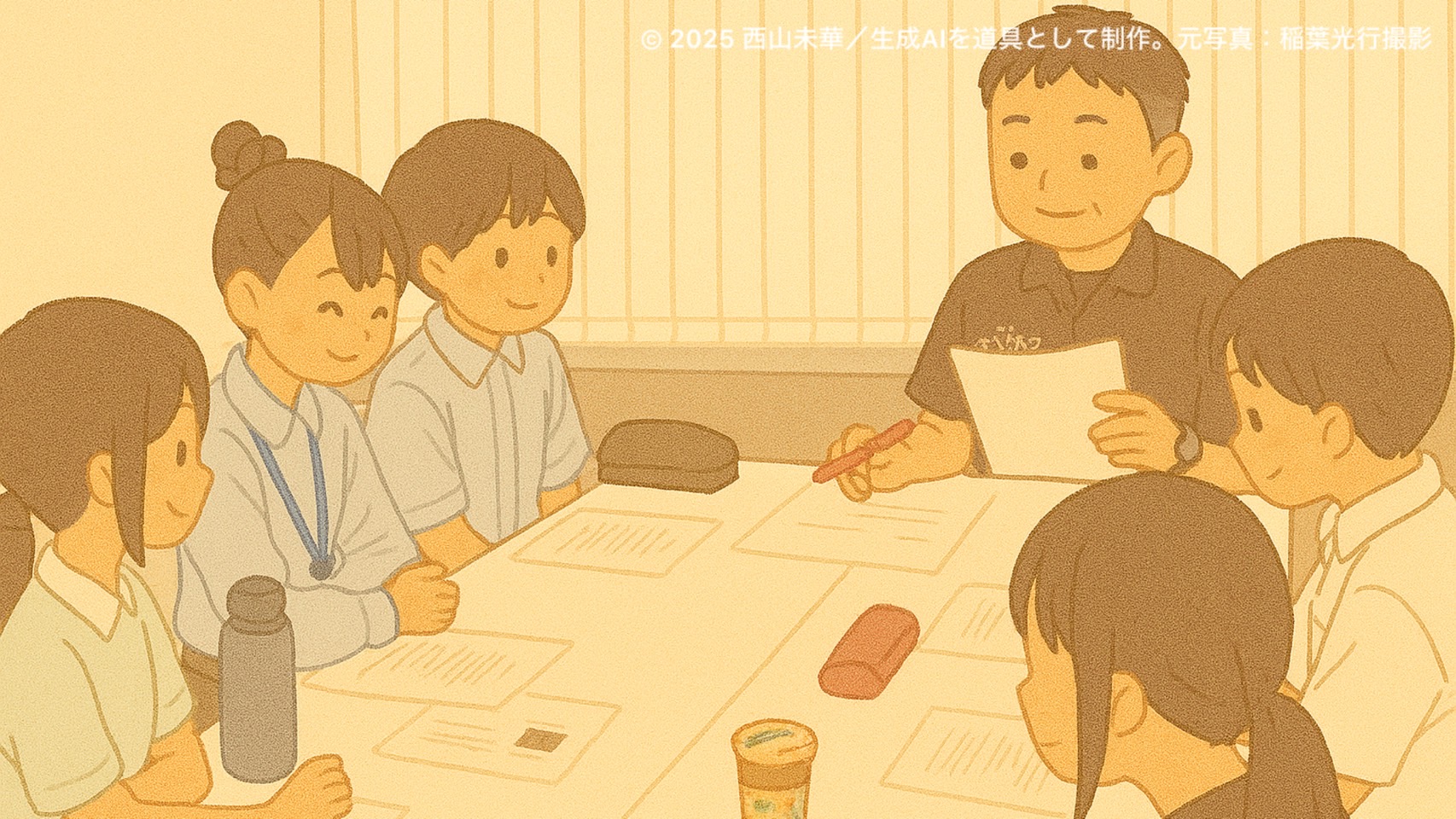
高校生班|イベントから動画制作へシフトチェンジ
高校生班は当初、多世代交流イベントを計画していました。しかし運営の難しさや課題が多いことを学びました。そこで彼らは方向転換。「防災啓発の動画を作ろう」と決意したのです。防災食の活用、起震車での体験、防災マップを使った避難訓練…。構想はどんどん広がります。消防署での取材も計画しており、実際の体験を映像にまとめていくことになりました。

ランチタイムは千本釣りで盛り上がり!
お昼休憩には大学生の企画で「千本釣り」が行われました。色とりどりのお菓子がぶら下がった紐を引っ張ると、どんなお菓子が当たるのか…。子どもたちの笑顔と歓声で会場は一気にお祭りのような盛り上がりを見せました。

市議会議場を特別見学
インタビューを終えた後は、市議会議場を特別に見学しました。来年1月にはここで市長に提言を行う予定です。堂々とした議場の雰囲気に、子どもたちは少し緊張しながらも目を輝かせていました。最後は全員で記念撮影。子どもたちにとって特別な思い出の一枚になりました。
